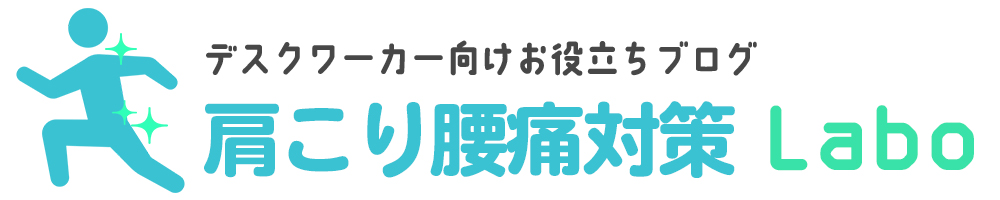東洋医学の“巡り”で通り道から整えませんか?
夕方になると肩が鉄板、立ち上がると腰がズーン——“押してラク→また戻る”の無限ループ、ありますよね。
東洋医学では、気・血・水(き・けつ・すい)の巡りが滞ると、筋のこわばりや重だるさとして現れる、と捉えます。
ツボとは?経絡上の「調整ポイント」のこと。
ツボ押しや灸で局所の巡りを促しつつ、姿勢と呼吸の通り道をセットで整えると、戻りにくさが育つ——これが鍼灸の発想です。
“巡り×姿勢”の二刀流で、同じケアでも戻り方が変わります。
この記事でわかること
- 肩こり・腰痛を“巡り×姿勢”で整える最新の考え方。
- 自宅でできるツボ押し・温灸のやり方と安全ポイント。
- 鍼灸院の選び方、医療受診の線引き、道具の上手な使い方。
まずは全体像を地図化しておくと迷いません。
原因→対策の流れは下記で俯瞰できます♪
【関連記事】:肩こり改善ロードマップ
結論:肩腰は“巡り(ツボ)×姿勢(呼吸・股関節)”の同時実装
結論はシンプル。
①巡り:肩は「肩井(けんせい)」「合谷(ごうこく)」、腰は「腎兪(じんゆ)」「殷門(いんもん)」など3点以内に絞ってやさしく刺激。
②姿勢:呼吸→胸ひらき→浅めヒップヒンジで通り道を作る。
③温め:灸や蒸しタオルで“冷え+こわばり”に点で熱を入れる。
これを30〜40秒×日に3〜6回回すのが現実解です。
“少数精鋭のツボ×短時間×高頻度”がいちばん続きます。
安全の線引きもセットで。
発熱背部痛、排尿排便異常、進行するしびれ・脱力、胸痛を伴う肩背部痛、外傷後の激痛/変形は自己ケアを中止し、速やかに医療へ。
迷ったら早見表を先にチェックしてから実践しましょう。
【関連記事】:受診の目安・危険サイン早見表
具体的な基礎テクニック|
「どこを、どう押す?」——やり方は“やさしく・短く・高頻度”。
痛みが鋭い日は中止してください。
“痛気持ちいい圧”で10秒×数回が基本です。
肩こり向け(合計3分)
1)合谷:親指と人差し指のまた。反対の親指で10秒×3回、心地よい圧で円を描く。
2)肩井:首根元と肩先の中間。指腹で10秒×3回ゆっくり押して離す。
3)天柱:後頭部のくぼみ外側。両手で支え、5秒×6回やさしく圧。
4)仕上げ:鼻で吸ってお腹を360°ふわっと→口から細く吐く×6呼吸、胸ひらき→浅めヒンジ×8回。
腰痛向け(合計3分)
1)腎兪:ウエストの高さ、背骨から指2本分外。親指で左右10秒×3回。
2)殷門:太もも裏中央。指腹で10秒×3回。椅子に座ってでもOK。
3)足三里:膝下外側のくぼみから指4本分下。10秒×3回。
4)仕上げ:骨盤コロコロ前後×10回→浅めヒンジ×8回。
灸(温灸・もぐさ・台座灸)を使う場合は低温タイプ/短時間から。
皮膚の赤みや痛みが出たら中止し、同じ場所に連日長時間は避けます。
ツボの位置に自信がない場合は、鍼灸院で触診の確認を受けると精度が上がります。
詳しいツボ押しの応用や注意点は下記で写真つきに整理しています♪
【関連記事】:肩こり改善のツボ押し完全ガイド
背景と現状分析
東洋医学は、気・血・水の滞りを“肩の板・腰の重さ・冷え”として捉え、経絡上の要所(ツボ)で流れを整えます。
一方で現代の不調は、長時間座位・画面凝視で呼吸が浅くなり腹圧が落ちることが土台になりやすい。
つまり「巡り」と「通り道」は同じ方向を向いているんです。
ツボで局所の流れを促し、呼吸→胸郭→股関節で大きな通路を開ける——この重ね方が戻りにくさを生みます。
“点(ツボ)”と“面(姿勢)”を重ねるのがカギです。
“環境のひと押し”も合わせると巡りが続きます。
モニター高・椅子・キーボードの10cm調整を整えると、首肩の“のぞき込み癖”が減ってツボの効果が乗りやすいですよ。
【関連記事】:デスクワーク姿勢大全
応用編:症状タイプ別ツボセット&季節・冷え対策
タイプ1:ガチガチ系(首肩の板、朝つらい)
・順番:温め→合谷→肩井→天柱→呼吸→胸ひらき→ヒンジ。
・ひと言:朝は蒸しタオル30秒を肩井へ、夜は入浴後に短時間の温灸。
タイプ2:重だる系(夕方つらい、むくみ気味)
・順番:足三里→殷門→腎兪→呼吸→骨盤コロコロ→ヒンジ。
・ひと言:水分はこまめに、塩分過多を控える。短時間の歩き(10分)を散りばめる。
タイプ3:ピリピリ・ビリッ(神経っぽい)
・順番:強い前屈/回旋は避け、横向き休息→呼吸→やさしいツボ1〜2点。
・ひと言:進行するしびれ・脱力、夜間痛は医療を優先。
季節・冷え対策
・冬:首・腹・仙骨を薄手で保温→入浴後の温灸を短時間。
・夏:直風を避け、腹まわりを冷やさない。冷飲過多は巡りを鈍らせがち。
道具選びは“使う場面×温度×肌への優しさ”で。
比較の目安は下記に一覧化しています♪
【関連記事】:温熱・温冷ケアグッズおすすめ2025
失敗しやすいパターンと改善
よくあるNG → 置き換え
・痛いほど強く押す → 心地よい圧×10秒を数回に分ける。
・1か所を長時間連打 → 3点以内で回し、日替わりで場所をずらす。
・温灸を熱いまま我慢 → 低温・短時間・皮膚観察を徹底。
・ツボだけで完結 → 呼吸→胸ひらき→ヒンジを必ずセットに。
“強さ”より“順番と頻度”が効きを決めます。
“ながらケア”と組み合わせると、続けやすさが段違いです。
家事や移動の隙間で差し込むアイデアは下記にまとまっています。
【関連記事】:肩腰ながらケア大全
FAQ(よくある質問)
Qツボの場所が合っているか自信がない…
A痛気持ちいい“反応点”に当たっていれば大きく外れていません。
不安なら鍼灸院で触診の確認を受けると精度が上がります。
Qどのくらいで効果を実感できる?
A個人差はありますが、30秒×3〜6回/日を3〜7日続けると“戻り方”の変化を感じやすいです。
Q鍼灸と病院、どちらが先?
A赤信号(発熱背部痛・排尿排便異常・進行しびれ/脱力・胸痛合併・外傷直後の激痛/変形)は医療が先。
それ以外は整形外科起点→鍼灸併用も選択肢です。
【関連記事】:整形外科医が解説する診断と治療の流れ
Qお灸は毎日してよい?
A皮膚の様子を観察しつつ短時間で。
赤み・水疱・かゆみが強ければ中止し、場所を日替わりで変えてください。
まとめ:要点3つ+行動提案(“ツボ3点×通り道”で戻りにくい肩と腰に)
東洋医学の強みは局所の巡りを点で促せること。
現代のセルフケアはそこに通り道(呼吸・胸郭・股関節)を重ねることで、日々の体が軽くなります。
完璧な長時間より、やさしく短く×高頻度。
そして“赤信号”は迷わず医療へ——これが安全で続く道なんですよね。
“ツボ3点×通り道”を今日から固定しましょう。
要点3つ
- ツボは3点以内(肩:合谷/肩井/天柱、腰:腎兪/殷門/足三里)。
- 仕上げは必ず呼吸→胸ひらき→浅めヒンジ。
- 灸は低温・短時間・皮膚観察。赤信号は自己ケア中止→医療へ。
今日からの行動提案(7日プラン)
- Day1–2:肩or腰のツボ3点×各10秒×3回+呼吸・ヒンジ(合計3分)。
- Day3–4:在席で“送信後30秒”の小ケアを固定。夜は入浴後に短時間の温灸。
- Day5–7:モニター高と椅子を10cm調整→歩き10分×2回を追加。効果の出た時間帯をメモして最適化。
“道具のひと押し”を使う時は、比較ページで条件を先に確認してから試すとミスマッチが減ります。
【関連記事】:鍼灸で肩こり改善
前向きなひと押し:完璧は不要。ツボ3点×通り道から始めれば、今日の肩と腰が少し軽くなります。
一緒に、やさしく続けていきましょう!
今回は以上です。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
気になる方は、ツボの詳しい押し方とデスク環境の整え方を合わせてチェックすると、効果が長持ちします。
【関連記事】:肩こり改善のツボ押し完全ガイド
【関連記事】:デスクワーク姿勢大全
関連記事リスト
【関連記事】:鍼灸で肩こり改善
【関連記事】:肩こり改善のツボ押し完全ガイド
【関連記事】:肩腰ながらケア大全
【関連記事】:受診の目安・危険サイン早見表