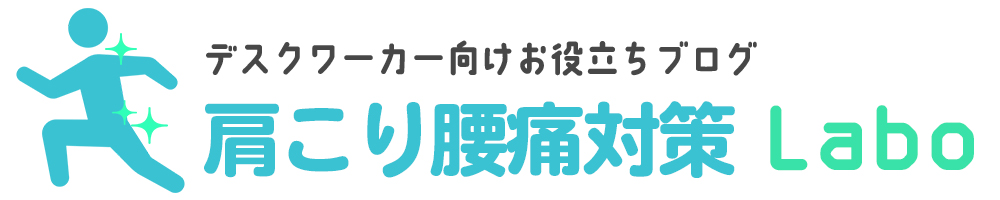夕方になると肩がパンパン…更年期の「いつもの肩こり」、実は仕組みがちがうかも
朝は平気なのに、午後になると肩まわりがずっしり重い。
天気や冷房の強さで調子がブレやすい。そんな波のある肩こりは、更年期のホルモン変化が関係しているケースが少なくありません。
僕も在宅勤務が増えた時期、気圧が下がると肩と首が一気に固まる日が続き、「姿勢だけの問題じゃないな」と気づいたんです。
ポイントは「原因がひとつではない」こと。筋肉だけでなく、血流や自律神経の揺らぎが絡み合って症状が出やすくなる時期なんです。
【関連記事】:肩こり改善ロードマップ|原因チェックからセルフケア・受診まで
結論:今日からできる対策は「温める・ほどく・支える」の三本柱
最初の一歩はシンプルです。
①温めて血流を上げる、
②肩甲骨まわりをやさしく動かして筋のこわばりをほどく
③仕事&睡眠環境を見直して首肩を“支える”。
この三本柱を日常のルーティンに落とし込むと、波のある肩こりでもブレにくくなります。
“短時間×回数”でこまめにケアするほど、夕方の重だるさがやわらぎやすくなります。
エストロゲンとは?
卵巣から分泌される女性ホルモンの一つ。血管や自律神経、筋・関節の調子をサポートする働きがあるとされます。
僕の場合は「朝シャワーで首後ろを温め→PC前の3分モビリティ→昼と夕方に肩甲骨リセット→就寝前に枕高さチェック」という流れで、夕方の重だるさがかなりマシに。だから、“短時間×回数”でこまめにケアするのが続けやすいんですよね。
チェックリスト(すぐ始める用)
- 首の付け根〜肩を湯船or蒸しタオルで3〜5分温める
- 1時間に1回、両肩すくめ→ストンの脱力を5回
- PCでは目線を上げる(ノートPCは台で底上げ)
- 寝具は「横向きでも首が沈みすぎない高さ」を基準に見直す
このあと具体的な手順を順番に深掘りします。より実践的な座り方・配置は下記で詳しくまとめています。
【関連記事】:デスクワーク姿勢大全|腰痛を防ぐ正しい座り方と改善法まとめ
グッズ活用も、タイミングが合うと効果を実感しやすいです。週3回の短時間ケアなら家電系のサポートも選択肢。価格や条件の比較はこちらに整理しています。
【関連記事】:肩こり改善マッサージ器ランキング|家庭用家電の効果比較2025
基礎テクニック:毎日の“ほぐす・支える・巡らせる”
「やらなきゃ」と気合を入れても、三日坊主で終わりがち…そんな方は“細切れケア”に切り替えてみましょう。
更年期は体調の波が出やすい時期。
良い日もあれば「今日は氷みたいに肩が固い…」という日もありますよね。
だからこそ、短時間で回数を重ねる発想が効きます。
“1回を短く、回数を増やす”ほど自律神経のブレに振り回されにくくなります。
自律神経とは?
心身の働きを自動で調整する神経のこと。呼吸・血流・体温などを24時間コントロールします。
まずは次のチェックから始めてみませんか?
チェックリスト(最初の一歩)
- 朝:蒸しタオルで首すじ〜肩を2〜3分温める
- 日中:1時間ごとに肩すくめ→ストン脱力を5回
- 夕方:肩甲骨を大きく回す(前後各10回)
- 就寝前:枕の高さを“横向きでも首が沈みすぎない”に調整する
具体的には、朝の温めは入浴手順が便利です。
「温め→動かす」の順にすると、筋のこわばりがほぐれて動きがラクになります。
【関連記事】:入浴で肩こり改善|温熱療法と血行促進の正しいやり方
次に、肩甲骨まわりの“二大リセット”を習慣化しましょう。
①肩すくめ→ストンで首肩の余計な力みをオフ、
②肩甲骨まわしで背中の大きな筋を動かして巡りをオンにします。
イスが「もっと楽に座ってよ」と文句を言っているイメージで、力を抜くタイミングを作るのがコツです。
座り方と画面位置の整え方は下記でご紹介しております。
【関連記事】:デスクワーク姿勢大全|腰痛を防ぐ正しい座り方と改善法まとめ
さらに、週2〜3回の“軽い筋トレ”を追加すると土台が安定します。
重いダンベルは不要で、肩甲骨を寄せるローイング系や壁プッシュアップで十分です。
体幹を支える筋が育つと、同じ作業でも肩の負担が減って夕方の重だるさが軽くなります。
種目選びは基礎メニューからどうぞ。
【関連記事】:肩こり改善に効く筋トレ入門|肩甲骨と背中を鍛える基本メニュー
ホルモンのゆらぎと自律神経の関係を知って、ブレない土台づくり
「同じ姿勢なのに、昨日は平気で今日はつらい」。
この“日替わり感”は、更年期のエストロゲン低下で自律神経のバランスが乱れやすいことが一因と考えられます。
血流や体温調節、筋のこわばりは自律神経の影響を受けやすく、ホルモンの揺らぎが重なると肩こりの波として表れやすいんです。
エストロゲンとは?
血管の拡張・収縮や体温調節、筋・関節のコンディションをサポートする女性ホルモンのこと。
更年期には分泌が大きく変動します。
データ的にも、40〜50代女性は肩こりや首のこりの訴えが増えやすいと報告があります。
数値は地域や調査で揺れますが、「症状が出やすい時期」と割り切り、生活習慣・作業環境・セルフケアを“合わせ技”で整えるのが現実的です。
実践では、その日の調子に合わせて“プランA/B/C”を用意しておくと迷いません。
コンディション別の引き出し(プランA/B/C)
- プランA(調子が良い日):軽い筋トレ+肩甲骨リセットで土台づくり。
- プランB(普通の日):温め→可動域づくりの順で負担を減らす。
- プランC(つらい日):温め+寝具の再調整だけに絞り、回復を優先。
寝具の最適化は肩だけでなく腰回りの違和感にも波及効果があります。
枕やマットレスの比較は次の記事が参考になります。
【関連記事】:肩こり腰痛に効く寝具ランキング|枕とマットレス徹底比較2025
「肩だけでなく腰や骨盤まわりも重い」。
そんな方は更年期腰痛の背景も押さえておくと、全体設計がラクになります。
【関連記事】:更年期腰痛の原因と改善法|女性ホルモンと骨盤ケアのポイント
応用編:生活環境・季節別の工夫
冷房の直下に座ると夕方に肩が石みたいに固まる…。
逆に冬は朝いちばんで筋肉が縮こまって動きが重たい…。
そんな“季節あるある”は、更年期のコンディションと重なると増幅されがちです。
更年期×季節の“二重のうねり”には、まず環境調整を先にやるのが近道です。
チェックリスト(環境&季節の見直し)
- 夏:冷房直撃を避け、薄手のカーディガンを常備。首すじだけは温かく保つ
- 冬:首後ろ〜肩を温めてから動かす(蒸しタオル3分→肩回し10回)
- 梅雨/気圧低下:作業時間を区切り、60分ごとに立つ“こま切れリセット”
- 通年:画面は目線より少し下、肘は90度前後、足裏は床にべったり
上のリストを“朝・昼・夕”の3コマに分けて、できることを一つずつ配置しましょう。
朝は温め+ゆるい可動域づくり、昼は座り方を直して肩の力みをオフ、夕は入浴で回復モードへ、という流れが王道です。
【関連記事】:在宅勤務の肩腰ケア大全|腰痛を防ぐ姿勢習慣とおすすめグッズ
季節の“うねり”には、温冷のメリハリも効きます。
入浴で芯まで温めた後、うなじを常温のシャワーで10秒流すだけでも、首肩の張りがスッと引く日があります。
【関連記事】:交代浴(温冷シャワー)のやり方|肩腰の血流を高める実践手順
食事面は「タンパク質+鉄+マグネシウム」を土台に。
筋と神経の働きが整うと、同じストレッチでも体の反応が変わります。
毎日の献立づくりに迷う日は、肩腰ケア向けの栄養の考え方もチェックしてみてください。
【関連記事】:肩こり腰痛を防ぐ栄養バランス|食事改善で整える2025年最新版
失敗しやすいパターンと改善策
「毎日1時間やる!」と気合い十分でスタートしても、三日で失速…。
更年期は体調の波が前提だからこそ、仕組みで続ける設計に切り替えましょう。
“やる気”ではなく“段取り”で積み上げるのが長続きのコツです。
チェックリスト(ありがち失敗→こう直す)
- 一度にやり過ぎる → “1分×3回”のミニセットに分割する
- 強度が高すぎる → “痛気持ちいい未満”で止め、翌日に余力を残す
- 姿勢が崩れっぱなし → “タイマー60分”で座り直しを合図化する
- 寝具が合っていない → 横向き時に首が沈みすぎない高さへ再調整する
実行率を上げるには、予定としてカレンダーに組み込むのが早道です。
朝:温め/昼:肩甲骨/夕:入浴を“固定イベント”にしてしまいましょう。
作業環境の見直しは効果の“持続時間”を伸ばす土台です。
【関連記事】:オフィス環境で肩腰痛を防ぐ方法|椅子・デスク改善マニュアル
そして、“我慢しない”も大切です。
しびれ・夜間痛・発熱・ふらつきなどのサインがある場合は、セルフケアより先に医療で確認を。
判断に迷うときは受診基準をチェックしておきましょう。
【関連記事】:受診の目安・危険サイン早見表|今すぐ受診?様子見?の基準
FAQ:気になりやすいポイントを先に解決
Q更年期の肩こりはどれくらい続きますか?
A個人差は大きいですが、数か月〜数年の波が一般的。体調の“良い日”に生活リズムを整えると揺れが小さくなりやすいです。
Qストレッチで悪化しませんか?
A痛みが強い日は“痛気持ちいい未満”で止めるのがコツ。温め→可動域づくり→軽い筋トレの順で段階的に行いましょう。
Q市販薬や湿布は使ってもいい?
A一時的な痛みの緩和には選択肢。長引く・しびれを伴う場合は医療で原因確認を。薬の選び方は下記が便利です。
【関連記事】:肩こり・腰痛に市販薬は効く?鎮痛薬・湿布の選び方
Q受診は何科に行けば良い?
Aまずは整形外科が基本。神経症状やめまいが強い場合は内科・脳神経内科なども検討。判断基準は下記で確認できます。
【関連記事】:受診の目安・危険サイン早見表
まとめ:要点3つ+今日からの行動プラン
更年期の肩こりは、ホルモンの揺らぎが自律神経や血流、筋のこわばりに影響し“日替わり”のつらさとして現れがちです。
だからこそ、姿勢や運動だけに頼らず、温め・可動域づくり・環境調整を合わせ技で設計するのが近道です。
“温め→ほどく→支える”の三本柱を、短時間×回数で日常化しましょう。
要点チェック(3つの核)
- 温め→ほどく→支えるの三本柱で“短時間×回数”を日常化
- 体調の波に応じてプランA/B/Cを用意(良い日=筋トレ、普通の日=温め+動かす、つらい日=温め+寝具見直し)
- 作業環境と睡眠環境の最適化が効果の“持続時間”を伸ばす土台
次に、今日からの行動プランをミニステップで。
まずは“1分でできるセット”から始め、2週間かけて段階的に厚みを増やしましょう。
行動プラン(2週間スモールスタート)
- Day1-3:朝の蒸しタオル2分→肩すくめ→ストン×5回/就寝前に枕高さチェック
- Day4-7:昼に肩甲骨まわし前後各10回を追加/ノートPCは台で底上げ
- Day8-10:入浴を活用(首〜肩を温めてからストレッチ)/座面の奥深く座るを合図化
- Day11-14:壁プッシュアップや軽いローイングを隔日で10回×2セット
“見える化”も効きます。
スマホのリマインダーで60分ごとに姿勢を直す合図を入れ、できた日はカレンダーに✓をつけるだけでも継続率が上がります。
イスが「今日は余計な力が入りすぎ!」と文句を言ってくるイメージで、肩の力を抜く合図をつくっておきましょう。
在宅とオフィスでは整え方が少し違うため、詳しい手順は次の記事がまとまっています。
【関連記事】:デスクワーク姿勢大全|腰痛を防ぐ正しい座り方と改善法まとめ
「自分はどのタイプの痛み?」と迷ったら、セルフチェック表も活用してください。
【関連記事】:肩こり腰痛セルフチェック表|症状別原因と改善法ナビ
関連記事リスト
【関連記事】:更年期腰痛の原因と改善法|女性ホルモンと骨盤ケアのポイント
【関連記事】:在宅勤務の肩腰ケア大全|腰痛を防ぐ姿勢習慣とおすすめグッズ
【関連記事】:肩こり改善グッズおすすめ大全|マッサージ器・ストレッチ器具効果徹底比較
【関連記事】:長時間PC作業で肩腰に負担をかけない工夫